少子高齢化の人口減少時代を迎え、介護など社会保険負担の増加とともに深刻になりつつあるのが空き家問題。誰も住まなくなった家は手入れがされないために老朽化で不動産の価値が下がる一方、管理の問題で思わぬ出費が発生します。親からの相続などで空き家を引き継いだ場合、早めの対策が必要となっています。
Contents
空き家問題とは

出典:pixabay
空き家問題は少子高齢化の人口減少時代を迎えて住む人のいなくなった住宅が増加することにより、その建物や敷地の管理に起因する社会問題です。こうした問題は過疎が進む地方圏はもとより、地方から都市部に移り住んだ当時の働き手であった「団塊の世代」の高齢化によって大都市圏でも深刻な問題となってきています。
そうした前の世代から引き継いだ不動産を、次の世代が受け継いで適正に管理できればよいのですが、そうした管理をすることは現実にはなかなか難しいのが実情です。
空き家問題の背景

出典:pixabay
現在、日本全国に或る空き家の多くが昭和の高度経済成長の時代に、当時の団塊の世代が「夢のマイホーム」として大量に建築され、購入された物件です。これらはすでに築後50年を経過しており、建築竣工から全く手が加えられていないとすれば、既に建物としての耐用年数は超えています。
また、これらの建物の多くが当時の耐震基準に基づいて設計されており、現在の耐震基準に適合していません。よって売買するにしても建物の安全性を重視する買い手のニーズとは一致しておらず、売却が難しいのが実情です。
空き家問題への対策

出典:pixabay
空き家問題への対策について関係法令が整備され、処分や売却を促進する方向性が明らかになりました。この方向性について次の3つのポイントで内容をチェックします。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家法)の施行
- 「特定空家」に指定されるとどうなる?
- 早期売却における税制上の優遇
空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家法)の施行

出典:pixabay
空家や空地を管理する責任は所有者にありますが、実際には放置されて建物の壁が崩れかけていたりして、破片が通行する人に当たったりしてケガをするケース、空地の除草などの管理が行われず、草が伸び放題、ゴミが投棄され放題といったケースが見られます。
そうした無責任な空家や空地の所有者に対して、地元の自治体である市役所や町役場などが助言や指導、勧告と言った行政指導の他、これらの指導に従わなかった場合に命令を発することができることを法律の条文に明記しました。
「特定空家」に指定されるとどうなる?

出典:pixabay
特定空家は空家等対策の推進に関する特別措置法で次のように定義されています。
第二条
2 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。(出典:電子政府の総合窓口e-Gov)
特定空家に指定されてしまうと、住居建て付け地としての固定資産税の優遇措置の適用除外となり、納める税金が増えてしまいます。なお、一旦特定空家に指定されてしまっても、行政指導に従って必要な修繕等を行うことで指定が解除される場合があります。
早期売却における税制上の優遇

出典:pixabay
親からの相続などで空き家を引き継いだ場合、早めに売却することで、売却によって発生した譲渡所得に対して、所得控除が受けられるケースがあります。
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。(出典:国税庁)
まとめ

出典:pixabay
過疎が続く地方部を中心に、日本全国にひろがりつつある空き家問題。空き家の情報については「空き家バンク」で把握することができます。相続などで引き継ぐ不動産の取り扱いにお困りの方が増える一方、所得が少ない昨今、地方の豊かな自然環境で暮らしたいご家庭も増えてきており、こうしたご家庭が地方に移住して新しい生活を始めることに政府の支援があれば、問題解決に役立つかもしれません。
最新情報をお届けします







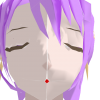




コメントを残す