本記事では相続税の対策について、対策が必要な場合とそうでない場合を解説し、対策が必要な場合に有効を思われる2つの方法をご紹介します。相続税が気になる方は是非チェックしてみて下さい。
Contents
相続税の対策が必要かどうかの確認方法

相続税が気になる方が最初にすることは相続税の対策が必要かどうか確認することです。
相続税は相続財産が一定金額を超える場合に、その超える部分について対象となる税金です。一定金額のことを基礎控除金額といい、次の式で計算します。
- 基礎控除金額=3,000万円+600万円×相続人の数
基礎控除金額は3,000万円を最低金額として相続人の数に対して600万円ずつ増加します。例えば相続人が2人なら5,000万円となります。
単純なケースで相続財産が預貯金だけの場合、相続人が2人なら預貯金が5,000万円に達しなければ相続税の対象外となり、相続税の対策は必要ありません。
相続税の対策は早めがベスト

相続税の対策は早めがベストです。その理由は相続税の対象となる財産を子や孫に贈与やその他の形で移すために相応の時間を要するからです。
相続が始まった際の財産の主な内訳が不動産の場合は難しいですが、預貯金などの金銭の場合だと贈与やその他の形で移すことは可能です。相応の時間を要するというのは贈与は一定金額を超えると非課税ではなくなる為で、非課税となる金額内で行う必要があるからです。
相続税の対策に有効な2つの方法

Fathromi RamdlonによるPixabayからの画像
相続税の対策には次の2つの方法が有効と言えます。
- 生前贈与で相続する財産を少なくする
- 保険の活用で節税する
生前贈与で相続する財産を少なくする方法、保険の活用で節税する方法のいずれも一方だけでなく同時併用によってより短い期間で相続する時点で財産を相続税の基礎控除金額以下にしておくことができます。
生前贈与で相続する財産を少なくする

生前贈与で相続する財産を少なくする方法に次のようなものがあります。
- 相続人に1人に年間110万円以内の贈与
- 教育資金贈与の活用
- おしどり贈与の活用
相続人に1人に年間110万円以内の贈与、教育資金贈与は子や孫を主な対象とした贈与で、おしどり贈与は配偶者への贈与です。
教育資金贈与は教育資金贈与信託を取り扱っている金融機関を通じた贈与で1,500万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。
おしどり贈与は婚姻期間20年以上のご夫婦で居住用不動産の贈与が対象となり、贈与税の非課税枠110万円にさらに2,000万円の非課税枠が使えます。
保険の活用で節税する

保険の活用で節税する方法に次の2つがあります。
- 保険金に対する相続税非課税枠の利用
- 生前贈与110万円以内を使い、贈与を受けた相続人が貯蓄性保険に加入
保険金に対する相続税非課税枠の利用の具体例として、「一時払い終身保険」という生命保険に被相続人が加入することがあります。万一相続人が死亡した場合、支払われる保険金には「500万円×法定相続人の数」の相続税非課税枠が設けられています。
生前贈与110万円以内を使い、贈与を受けた相続人が貯蓄性保険に加入する例として、贈与された子供や孫が自己名義で貯蓄性保険に加入、保険料の支払いを行い、満期になったら保険金を受け取るという形になります。
満期になった保険金には所得税がかかりますが、保険に加入していた期間がある程度の長期になると税率はかなり低くなりますし、毎年の保険料は所得控除の対象となりますのでその点でも節税の恩恵があります。
不動産投資は有効とは言えない

Nattanan KanchanapratによるPixabayからの画像
相続財産が土地などの不動産が殆どの場合は、毎年贈与という方法は難しくなります。こうした理由から相続税対策として土地を活用した賃貸マンションや賃貸アパートを建築して土地の評価額を引き下げて相続税対策する方がいます。
こうした不動産投資は相応のノウハウがない素人では失敗のリスクを抱えることになりますし、テナント募集のための広告費や建物の維持補修に要するコスト、そして将来の相続財産の対象となることを考えると相続税対策として有効とは言えません。
相続税の対策で注意すること

相続税の対策で注意することは税務署から不審な印象を持たれないようにすることです。そのためには生前贈与の金額や開始時期に不自然な点がないようにしたほうがいいでしょう。具体的には次のようなことに注意します。
- 贈与契約書を毎年作成する
- 贈与した財産の管理は贈与を受けた人に任せる
なお、相続開始から3年以内の贈与財産は相続財産から除外とはならない点についても注意が必要です。
まとめ

相続税はお金持ちだけが対象の税金と思っていたら、税務署から通知が来たということにならないように、聞きにくい面がありますがお父さんやお母さんに「うちの財産いくら位あるの」と聞いておく方がいいかもしれません。預貯金などはすぐに確認出来ますが不動産に関しては固定資産税の納税通知にある固定資産の評価額を確認するなどしておけば大体の金額はわかるでしょう。
相続税の基礎控除となる金額が近年の税制改正で大幅に引き下げられましたので、相続税はお金持ちだけの税金という認識を改める必要があるのかもしれません。相続に関係する税金の対策は早めに行うほど有利です。
最新情報をお届けします
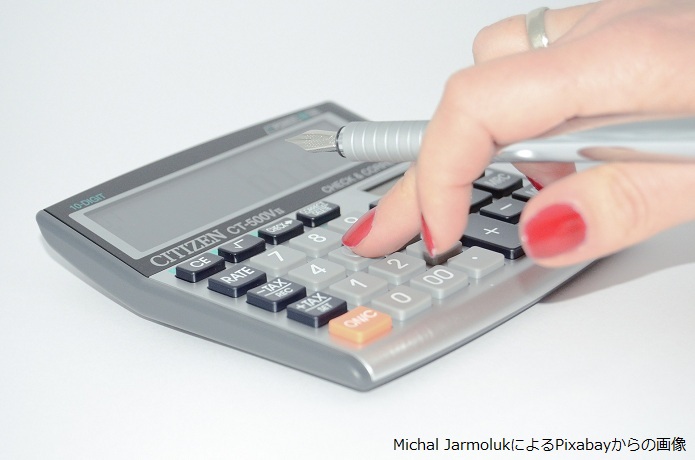











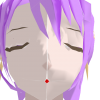


コメントを残す