債券は証券として株式とは違う特徴を有しています。本記事では債券についてご紹介し、併せて投資における長所と短所、関連する基礎的な知識について解説します。投資に興味がある、債券について知りたい方はチェックしてみて下さい。
Contents
債券とは

債券とは特定の会社などにお金を貸付ける形で投資を行うために発行される証券で、投資したい人は債券と呼ばれる証券を購入します。
企業や政府機関は事業活動を行うために必要なお金を広く社会一般から集めるために社債や国債と呼ばれる債券を発行し買い手を募って売却します。売却された債券はその後に市場と呼ばれる売り手と買い手が集まる場で売買取引されることでその価格が決まります。
債券のうちで最も多く発行されているものは国債です。国債は国が発行する債券で保有している間は定期的に利子を受け取り、満期になると元本が還ってきます。国債は郵便局などの金融機関に行けば個人でも購入できる最も身近な債券です。
債券の長所

債券投資の長所に次のことがあります。
- 投資としては株式に比べるとリスクは少ない
- 中途売却せず、満期償還まで保有すれば元本割れする危険性はほぼない
- 定期預金などに比べて利息が高い
- リターンに及ぼす景気変動の影響が少ない
株式との比較において、債券は利益率が高い金融商品であるとは言えませんが、それでも定期預金などに比べて利息が高いと言える金融商品です。債券には国債や地方債といった政府や地方自治体なご行政機関が発行するもの以外に、社債と呼ばれる民間企業が発行するものがあり、本記事執筆の2019年9月時点のではソフトバンクグループが売り出している社債が注目されているようです。
債券の短所

債券投資の短所に次のことがあります。
- 投資としては株式に比べるとリターンは少ない
- 満期償還まで保有せず、中途売却する場合に売却時期によって元本割れする危険性がある
- 金利、為替変動の影響を受ける
- 日本を代表するような会社の社債は購入にまとまったお金が必要
債券は株式ほど価格変動が大きい金融商品ではないので、値上がり益の点では魅力は少ないと言えます。債券の場合も株式と同様に売り手と買い手の力関係で価格変動がありますが、同時に利回りも変動するので中途売却しなければ実質的なリターンは安定しています。
債券の利子率は市場金利、特に長期金利の影響を受けます。また外国の政府や企業が発行する外国債の場合には為替変動の影響を受けます。為替が有利に働けば株式に近い利回りとなることもありますが、不利に働けば元本割れすることもあります。
債券の平均的な利回り

債券投資の平均的な利回りは投資する債券による差がありますが、国内債券で0.33~0.35%程度(税引後)は期待できます。ただし銘柄によって利回りに違いがあるのも債券の特徴で、2019年9月に売り出しが予定されているソフトバンクグループの社債の場合、年1.20~1.80%(税引後で年0.956~1.434%)と高い利回りで注目を集めています。
信用力の高い企業や団体の発行する債券は利回りが低く、債券は高い値段で取引されています。逆に信用力の低い企業や団体の発行する債券は利回りが高く、債券は安い値段で取引されている場合が多いです。
よって投資する債券を選ぶ際は利回りの高さだけでなく、ムーディーズやスタンダードアンドプアーズのような格付け機関が付ける格付けが高いことを確認することが重要です。
一般的に国内債券の利回りは国内株式に及びませんが、外国債券の場合は為替の影響を受けるために国内株式と同じくらいの利回りとなることが期待できます。ただし、利回りの高い債券はリスクも大きくなるので注意が必要です。
債券の利回りは購入のタイミングで違う

債券の利回りは購入のタイミングごとに計算方法が変わる点に特徴があります。具体的には次の3つがあります。
- 応募者利回り:新規発行時に購入した債券を満期まで保有し続けた場合の利回り
- 所有期間利回り:発行済み債券を購入し、満期までの途中で売却する場合の利回り
- 最終利回り:発行済み債券を購入し、満期まで保有し続けた場合の利回り
債券の利回りの計算式は単利の利付き債券の場合、次のように記述できます。
- 債券の利回り(%)=【表面利息+(価格A-価格B)÷期間C】÷価格B
- 表面利息=表面利率×額面金額
価格A、価格Bおよび期間Cについて、応募者利回りの場合で次のようになります。
- 価格A:額面金額
- 価格B:発行価格(入札価格)
- 期間C:発行日から満期日までの期間(償還期間)
所有期間利回りの場合で次のようになります。
- 価格A:売却金額
- 価格B:購入価格
- 期間C:購入日から売却日までの期間(所有期間)
最終利回りの場合で次のようになります。
- 価格A:額面金額
- 価格B:購入価格
- 期間C:購入日から満期日までの期間(残存期間)
債券は満期日に額面金額で償還される(額面で発行主体が引き取る)ことが分かっているので値上がりしたからといって満期までの途中で売却したりせず、満期まで持ち続ける方がよりリスクが減ると考えておくといいでしょう。
債券に関連する基礎知識

債券に関連する基礎知識として、投資する債券を選ぶ際に目安となる基準や債券の価格に影響する経済要因、債券投資の始め方や税金について解説します。
投資する債券を選ぶ際に目安となる基準

債券には政府やそれに準じた機関が発行する公債と民間企業が発行する社債の他、外国債などの海外債券、株式に転換できる転換社債など様々で多くの種類があります。
債券は利回りが良ければ全て良いという金融商品ではない点に注意が必要です。株式と同じで利率が高い金融商品になるほど大きな損失を受ける危険があります。
基本的には満期まで保有していれば発行主体が経済破綻しなければ元本割れしない金融商品なので満期まで保有することを前提に、表面利率が高く、格付け機関の評価が高い銘柄を選ぶといいでしょう。
金利と価格の関係

債券の価格は金利と密接に関係しており、一般的に債券価格は金利が上昇すれば下落し、金利が下落すれば上昇します。
株価との関係も注目すべき点で、金利が上昇すれば株を売って債券を買う人が増えます。理由は株価が下がるとともに高い金利の債券を割安で買うことができるからです。逆に金利が下落すれば株価が上がるとともに価格の上昇が見込めない債券を売って価格の上昇が見込める株を買う人が増えます。
利付債と割引債の違い

利付債は表面利率で示される定期的な利息がある債券で、額面金額の割引がない債券です。これに対して割引債は表面利率で示される定期的な利息がない債券で、額面金額の割引がある債券です。
割引債は額面金額より安い購入価格が特徴で、額面金額と購入価格の差額が実質的な利息となる債券と言えます。国が発行する債券である国債には利付債と割引債の両方があります。
債券投資の始め方と税金

国債は郵便局などの金融機関で申し込むことで購入することができます。国債などの公債以外、例えば社債の場合だと買いたい社債の取扱がある証券会社に一定の手順に従って取引口座を作れば購入することができます。
税金に関して債券の購入時に消費税などはかかりませんが、取引で生じた利益や償還までに受け取る利息には所得税および住民税が課税されます。税率は所得税と住民税を合わせて20.315%です。
利付債と割引債では利息や売却益で所得区分が異なり、具体的には次のようになります。
- 利付債:保有時に受け取る利息には利子所得として所得税および住民税が課税
- 利付債:償還や売却に伴う差益には譲渡所得として所得税および住民税が課税
- 割引債:償還や売却に伴う差益には譲渡所得として所得税および住民税が課税
債券のまとめ

債券は同じ証券である株式に比べて一般的に利回りの魅力は薄いものの、満期まで保有することで安定した利息が定期的に得られ、満期には償還されて元本が戻ってくる極めて安定した資産運用が可能な金融商品です。
ただし、債券は種類が多くて中には株式に劣らない利回りを示す仕組債と呼ばれる債券も存在しています。こうした債券は高い利回りと引き替えに債券を発行する組織や団体の信用が低い場合や経営破綻のリスクがある、または為替変動を組み入れているなどの場合があり、債券を選ぶ場合は利回りの高さだけではなく、債券の格付けや高い利回りがなぜ実現できるのかについて調べておく方がいいでしょう。
最新情報をお届けします












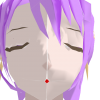

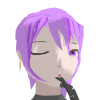
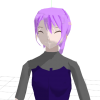
コメントを残す