仕事をしていただく賃金やお給料から生活に必要なモノを買ったり、サービスを利用することで出ていくお金を差し引いた残りは金融機関に預けたり、手元に持っておく方もおられるでしょう。こうしたお金をさらに殖やすといった場合、金融機関に預けることが、長い間にわたり美徳とされてきました。
貯蓄とは

出典:pixabay
貯蓄とはリスクを避けた状態でお金を金融機関に預けたり、家の中の金庫に保管することを指し、お金を殖やす目的で行う投資より、節約して残ったお金を貯めていくことを重視しています。節約して残ったお金がある限り、お金が減る危険がある投資より安全で確実と言えます。また、金融機関の預けた場合は一定金額までの預金は保証されることがペイオフ制度に定められています。
貯蓄はいずれは消費になったり、投資になったりするのですが、消費でも投資でもない形の資産保有手段で、節約を美徳とする日本の文化とともに、日常生活で定着してきました。しかし、最近はこうした貯蓄偏重の考え方から積極的に投資で殖やそうといった流れになりつつあるようです。
貯蓄と消費の違い

出典:pixabay
労働の対価や事業の収益として得たお金の一部は衣食住に必要な消費に充てられ、残ったお金は将来への消費行動に備えて、現時点では消費されずに金融機関に預けたり、タンス預金として持っておくことがあります。
消費と貯蓄の違いは、現時点でのお金の支出であるか、将来の予定された時点でのお金の支出であるかの違いだけで、現時点で貯蓄の形で残っているお金もいずれは消費、または投資となって経済活動のお金の流れに戻っていきます。
貯蓄と投資の違い

出典:pixabay
貯蓄と投資の違いは、貯蓄がお金を安全重視で貯めていくことを目的としているのに対し、投資はお金を働かせることで、お金でお金を殖やすことを目的としていることです。
貯蓄にはリスクやリターンといった概念がほぼ皆無に近いのに比べ、投資ではリスクやリターンといった概念がとても重要。リスクやリターンは投資対象によって日々変化するので、そうした変化に合わせて投資対象の構成を見直すなどのメンテナンスが必要となります。こうした面倒なことや専門的な知識が必要なことが投資より貯蓄が多い理由の一つと言えるでしょう。
貯蓄が優遇された理由

出典:pixabay
高度経済成長期の日本では、貯蓄が大いに奨励され、マル優制度(少額貯蓄非課税制度)などの税制上の優遇もありました。会社の福利厚生の一環で財形貯蓄を奨励している会社は今も数多くあるでしょう。
こうした貯蓄が優遇された背景に、ライフプランを考えたお金の付き合い方を奨励する面もありましたが、貯蓄として金融機関に預けられた預金が金融の仕組みを通じて広く社会への投資資金となり、その資金で産業を興して経済を活性化させる政府の政策的な目的もあったと言えます。
貯蓄が多い国の通貨はどうなる?

出典:pixabay
貯蓄が多い国は国内の投資に回せる資金が豊富にあるということで、経済成長に必要な資本に恵まれている国と言えるでしょう。また貯蓄は将来の消費ということで考えれば消費余力も有しているという理解もできます。将来への不安が解消されれば、今は貯蓄でも消費に回る可能性があります。
また、財政の面でも破綻のリスクが少ないと好意的に受け止められるでしょう。日本の財政は世界で飛び抜けて赤字ですが、その赤字を補填するための国債を買っているのは日本国民が殆どだという説もあります。低金利で預金しても利息が付かないと考えた人の多くが、金融機関への預金より利息がついて、比較的安全な国債で貯蓄のお金を運用しているのかもしれません。
貯蓄が多い国の通貨は低金利であっても、国の財政破綻のリスクが少なく安全だという理解から、リスクを避ける際の一時的な待避の目的で買われることが多くなります。そしてリスクがある程度解消した状態では、よりリターンが狙える通貨を買うために売られることになるでしょう。
まとめ

出典:pixabay
貯蓄はリスクを避けてお金という資産を守る目的で手段として選択されることが多く、特にお年寄りは少子高齢化で自らの老後の年金不安や健康不安などから、万一のために金融機関に預けるよりタンス預金として手元にお金を持っておきたいという方が多いのではないでしょうか。
こうしたお金は消費や投資といった経済活動に投入されることはなく、景気を悪化させる要因の一つになります。こうした将来への不安を解消させ、国民が安心して消費や投資ができる環境作りが政府の役割として重要になっています。
最新情報をお届けします















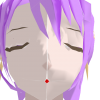




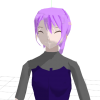

コメントを残す